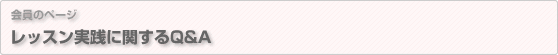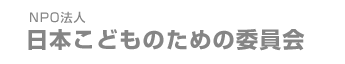 |
(事務局) 〒156-0043 東京都世田谷区松原5-2-6-3E TEL:03-5329-1461 FAX:03-5329-1491 E-mail:renraku@cfc-j.org |
|
| TOP>会員のページ>レッスン実践に関するQ&A | ||
|
|
| すでに出版されている教材コース1は、小学校の低学年までが対象です(実際は、日本では高学年にも使っている実態があります)。高学年の小学生向けはコース4となります。中学生版はまだ翻訳されていません。 |
| 今のところ紹介はしていませんが、今後CFCJで努力したいと思います。お近くの保育園や児童館に出かけて、セカンドステップの説明をなさると、実践させてもらえるところが見つかるかもしれません。 |
| ホームページに実践している場所が掲載されています。そこに直接連絡なさるか、事務局までお電話いただければご紹介できると思います。 |
| 会に連絡していただければ、ありがたいです。 |
| 指導員になるまで、自己負担となります。保育園、児童館などで実践する場合は、そこのコピーを使うようにおねがいしてはいかがでしょうか。 |
| ▲トップへ戻る |
| 実践は研修を受けた方だけができる、ということになっています。それは、セカンドステップについて、正しい理解をもっているかどうか保障ができないからです。 |
| 30人ぐらいまで可能ですが、理想は10数人ぐらいです。そのほうが発言したり、ロールプレイをしたりする機会が増えて、スキルが身につくと思います。 |
| 悪いとは言えませんが、セカンドステップが期待する効果は、十分には出ないかもしれません。その理由のひとつは、ブレーンストーミングが幅広くできないからです。つまり、解決策が多様にでないので、一定の枠内でしかレッスンを展開できません。 また、これは大事なことですが、友だちと一緒に楽しみ、意見を聞いたり、ロールプレイを見たりする機会がなく、ソーシャルな体験が得られない難点があります。 |
| 順番にすることが理想的です。1章は2章の基礎となり、3章は1章と2章を踏まえた応用編です。 順次、必要なスキルを積み重ねていくようにプログラムが作られております。 従って、順番にした方が効果が出てきます。 ただし、時間のない方のために組まれた「20回プログラム」というものもありますので、事務局までご相談ください。 |
| レッスンはスキルを学ぶ一つの事例です。大事なことは、日常生活でセカンドステップのスキルが使われていることなので、そのような日常生活であれば、2週間、3週間の間隔が開いても、効果はあると思います。 |
| ▲トップへ戻る |
|
その場合は、1週間に一つのレッスンを2回あるいは3回にわけてやる方法があります。 |
|
4,5才の子どもにしばしば見られ、立ち歩かないように指導者が注意していると、レッスンの雰囲気が途中で変わって、すっきり進まないことがあります。 |
|
「最後まで」を「レッスンが終わるまで」と解釈してお答えします。レッスン中、ひと言も発言しない子どもはレッスンに参加していないかというと、必ずしもそうではない事例をいくつも確認しております。極端には28レッスンをほとんど発言しないで修了した子どもが、日常生活の中で、セカンドステップのスキルをちゃんと使っている例もあります。 |
| 「レッスンの内容を理解できない子ども」が、知的な障害を持っている子どもではない、という前提で、お答えします。 レッスンは、行動の仕方の一つのモデルを示しており、実際の生活場面で、そのモデルを模倣する必要があります。同じ4才の子どもでも、月齢によって、あるいは個人によって、知的な理解度に大きな開きがあり、実際に第2章の「問題解決」のレッスンになると、3才に近い4才の場合、理解が十分に出来ない例があります。 このような場合は、日常生活の場面で、先生や指導者たち大人が、セカンドステップのスキルを使って、子どもたちと接するように心がけると、生活場面からレッスン内容を身につけ、理解することができるようです。 セカンドステップは、知識を教えることを目的にしてはおらず、行動の仕方を身につけることを目的にしたプログラムである、ということができると思います。 場合によっては、28レッスンをもう一度実施するとよく分かることがあるます。 |
| Q13で触れましたが、どのレッスンも第1回目のレッスンで作った「みんなの約束」に注意を向けてから始めるとよいでしょう。 「みんなの約束」を前提にレッスンを進めるとき、わざとおかしな発言を、本人はふざけてしたかもしれませんが(あるいは、ふざけているようにみえるだけかもしれません)、ブレーンストーミングでは、それも良しとします(反社会的な発言も良しとします)ので、心配することはありません。 注意すると、ブレーンストーミングの意図が失われます。それも解決策の一つと考えましょう。問題の解決策として、それが適当かどうかは、チェックポイント(安全?気持ちは?フェア?解決できる?)でチェックすればいいわけです。 |
| ▲トップへ戻る |
| |TOP|セカンドステップって|活動内容|研修会と資格|関連情報|プレス| |日本こどものための委員会|入会案内|会員のページ|お問い合わせ|サイトマップ| |